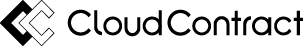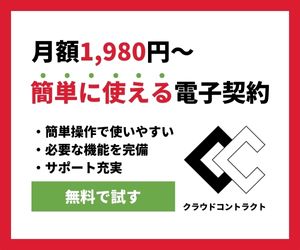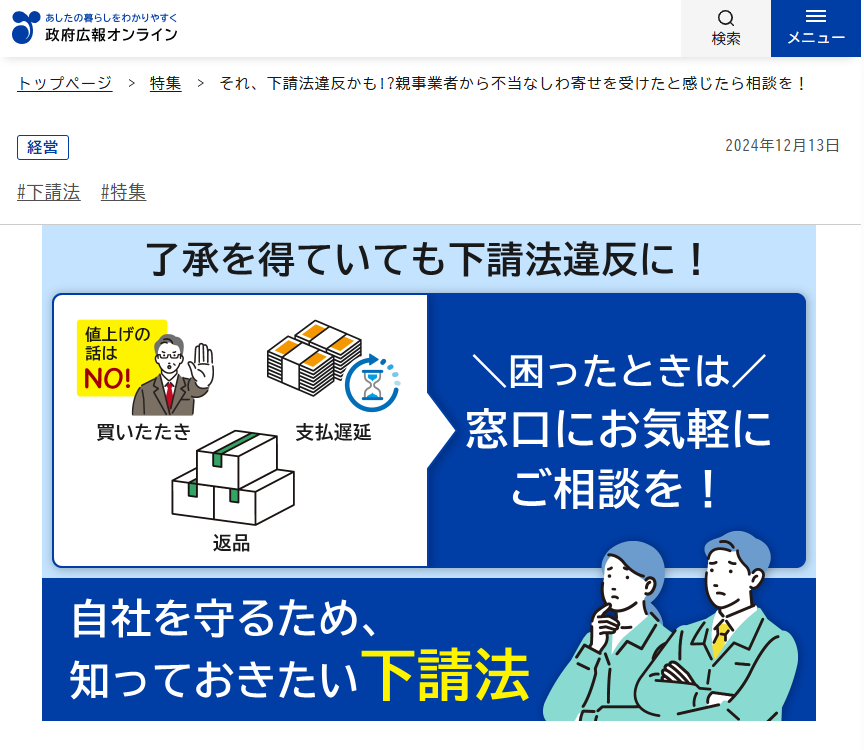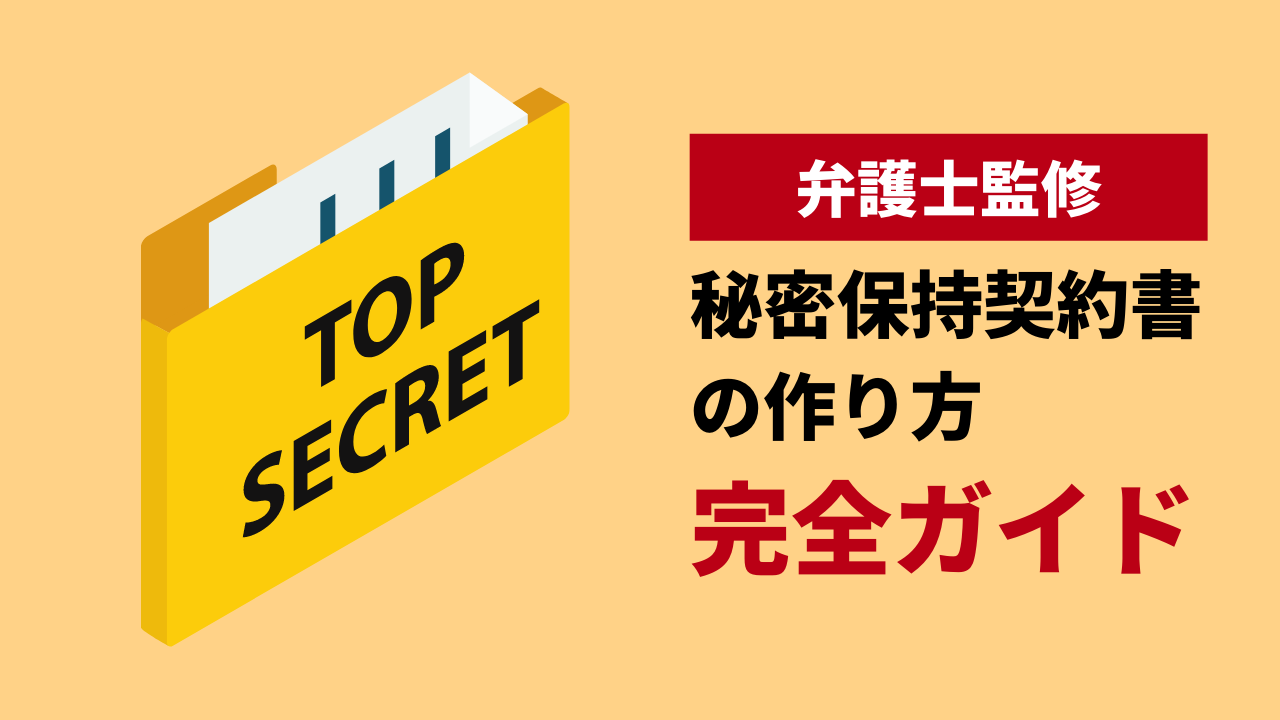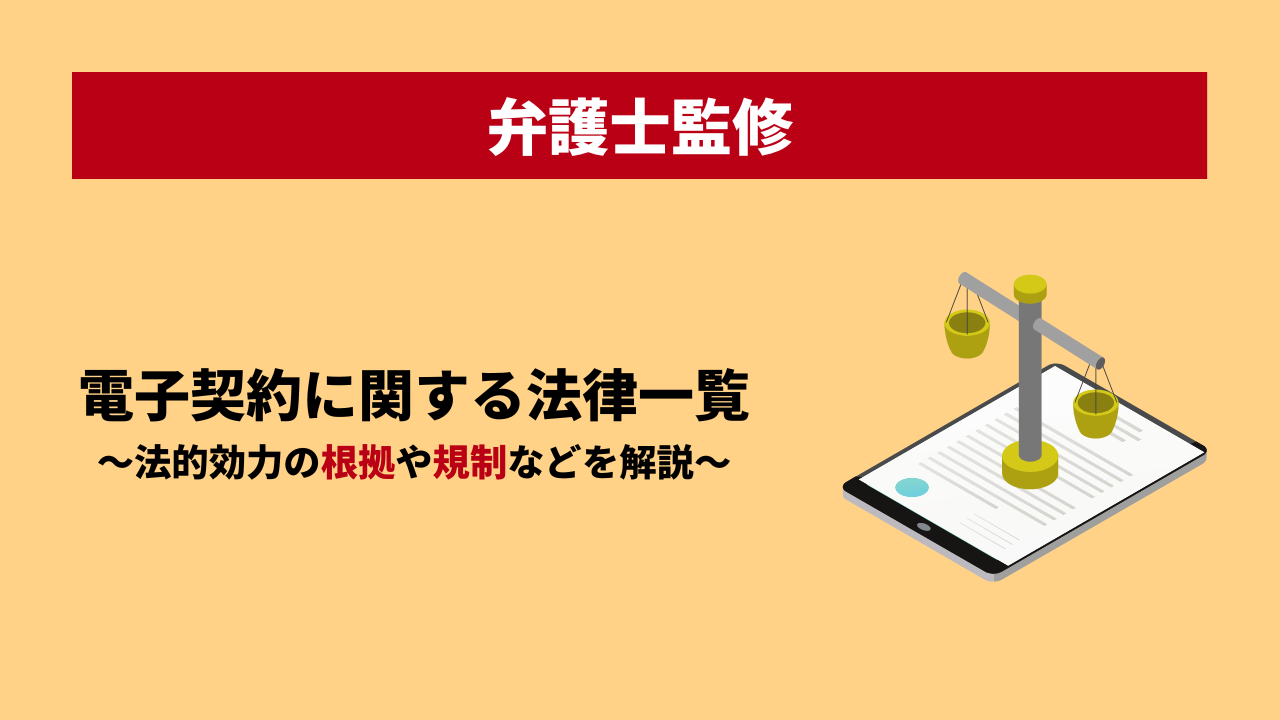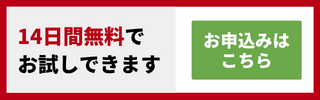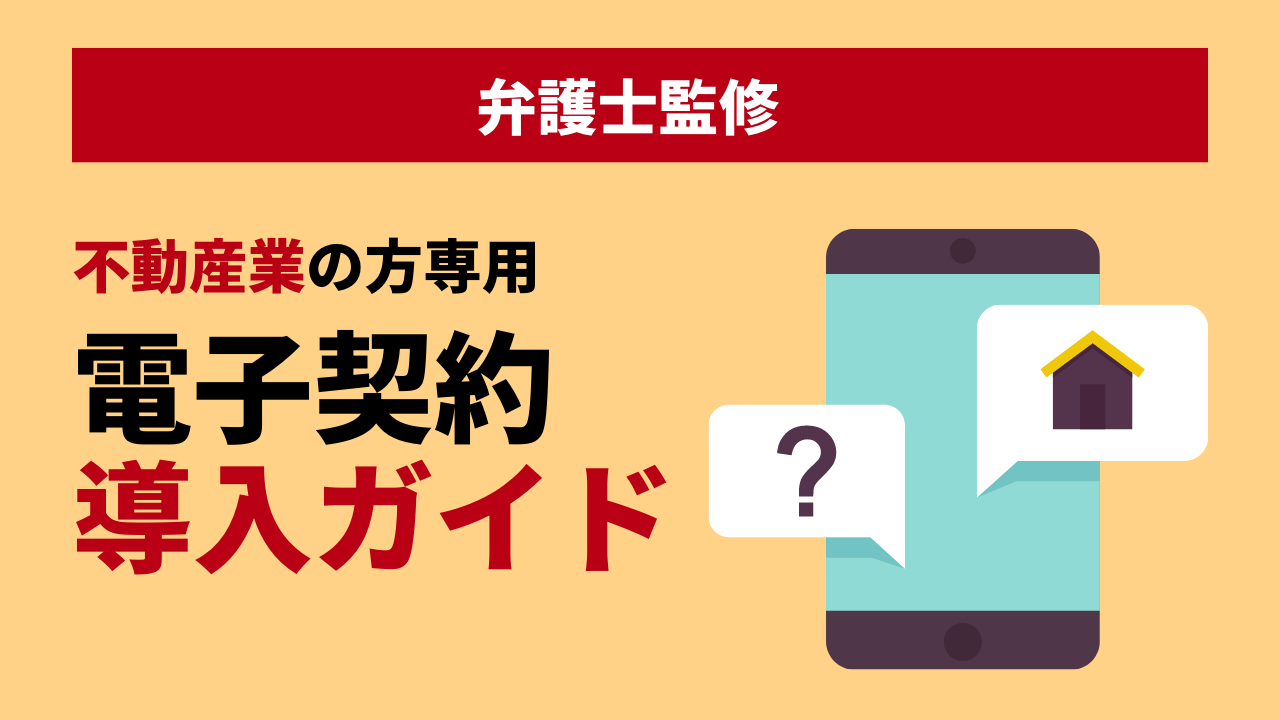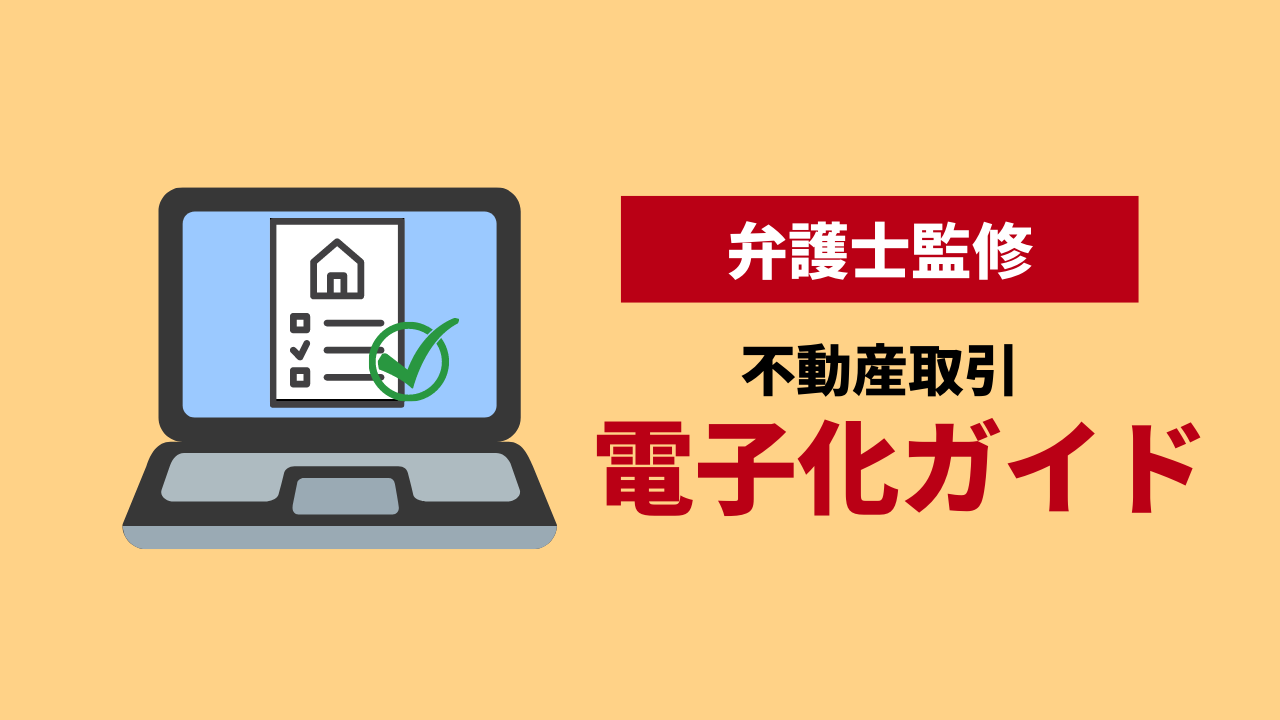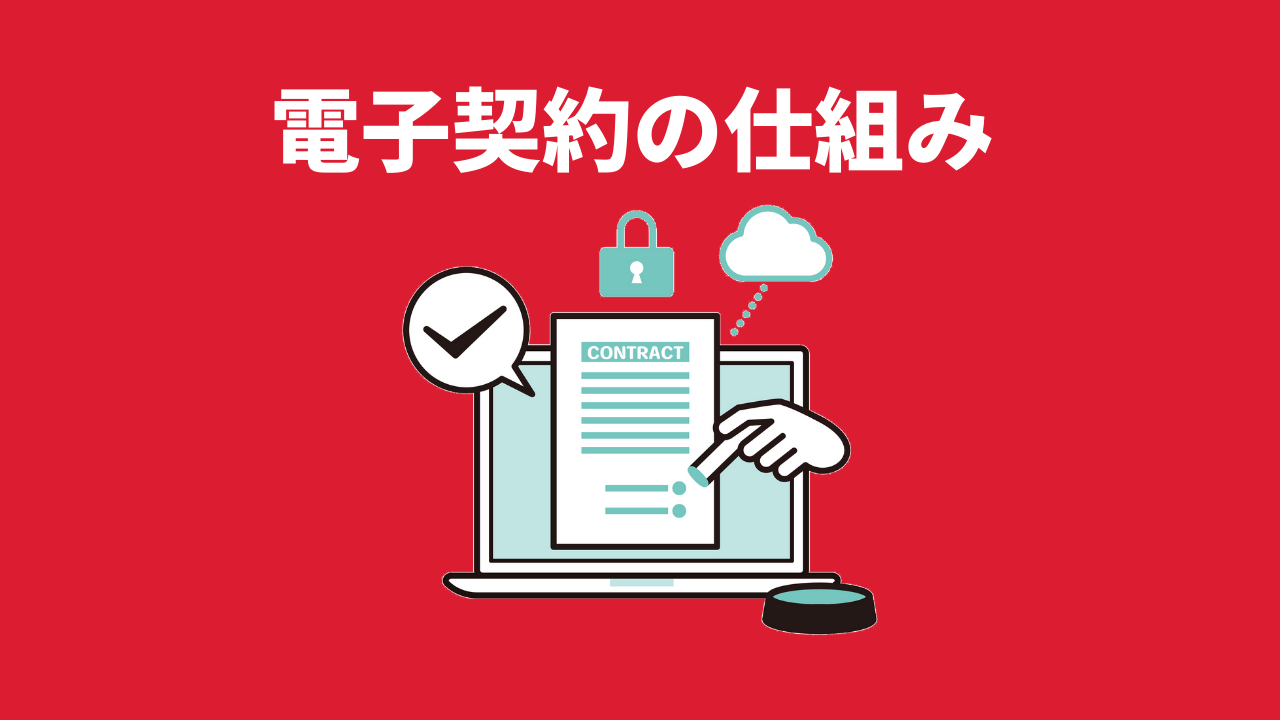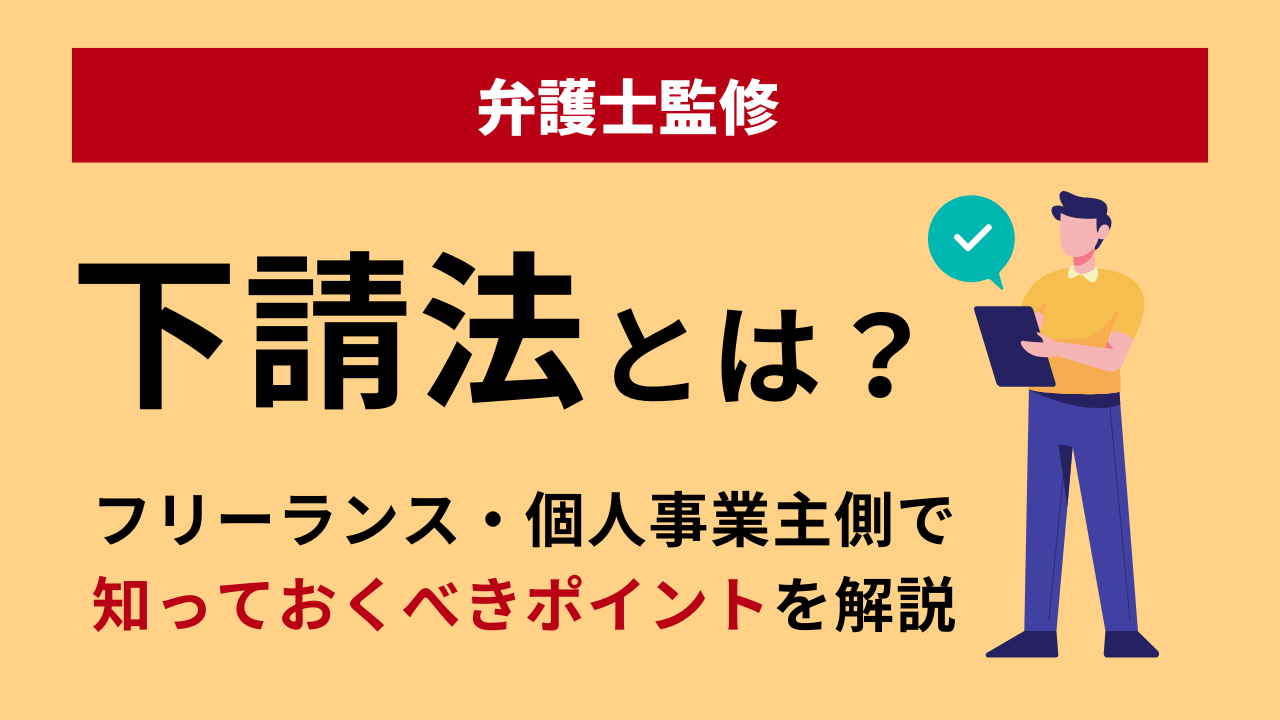
下請法とは、元々、中小企業を下請とする事業者間の公正な取引の確保や、下請業者を保護するために制定された法律ですが、近年の働き方の多様化により、フリーランスや個人事業主が関わる取引も下請法の対象となるケースが増えています。
当記事では、フリーランスや個人事業主として事業を行う場合に知っておくべき下請法についてわかりやすく解説し、万が一違反があった場合の対処法もご紹介します
下請法とは?
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。
下請法は、取引の際に有利となることの多い元請業者(=発注元)の業務の適正化と、「親事業者」となる下請業者(=発注先)の保護を目的とする法律です。
正式名称の通り、元請業者による支払いの遅延(60日以内に支払いを行わないこと)や、返品を強要することなど、様々な行為が禁止条項として定められています。
下請法に抵触すると、公正取引員会からの勧告や公表、罰金、支払遅延利息の発生など、様々なペナルティが元請業者に課せられます。
下請法の対象となる取引
下請法の対象となる取引内容は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4つに分けられます。
【1】製造委託
製造委託は、元請業者が、規格や品質などを指定して物品の製造や加工を他の事業者に発注する行為が該当します。物品の製造や加工のみならず、修理を請け負う業者がその物品の修理のために必要な部品・原材料の製造を依頼するなどの場合もあるため、半完成品の製造を委託する取引も含まれます。
例)
- 自動車メーカーが自動車部品の製造を他の事業者(自動車部品メーカー等)に委託する場合
- 食品メーカーが自社商品の製造を他の事業者(食品加工会社等)に委託する場合
- 衣料品メーカーが衣料品の縫製を他の事業者(縫製工場等)に委託する場合
【2】修理委託
修理委託は、元請業者が規格や品質などを指定して物品の修理を他の事業者に委託する行為です。元請業者が修理を請け負っている修理行為を他の事業者に委託する場合、元請業者が自社で使用する物品の修理を、他の事業者に委託する場合のどちらのケースも該当します。
例)
- 自動車メーカーが自動車修理を自動車修理工場に委託する場合
- 家電メーカーが商品の修理を家電修理会社等に委託する場合
- 自社の工場で使用している機械の修理を機械修理業者に委託する場合
【3】情報成果物作成委託
情報成果物作成委託は、元請業者が情報成果物の作成を他の事業者に委託する行為を指します。プログラムやソフトウェアの開発、デザインの作成、映像の制作など、情報に関する成果物の制作に関する幅広い業務が含まれます。
例)
- ソフトウェア開発会社がプログラムの一部をソフトウェア開発会社等に委託する場合
- 広告代理店がCMの制作を映像制作会社に委託する場合
- 出版社が書籍の装丁をブックデザイナーに委託する場合
【4】役務提供委託
役務提供委託は、元請業者が他の事業者に人の手を伴うサービスの提供や作業を委託する行為を指します。物品の製造や修理、情報成果物の作成以外の、建物の警備や清掃、運送、メンテナンス、ソフトウェアの保守管理など、幅広いサービスに関する委託が該当します。ただし、建設工事に関する委託については、建設業法が適用されるため、下請法の対象外となります。
例)
- イベント運営会社がイベント開催時の警備を警備会社に委託する場合
- ビルメンテナンス会社が定期清掃を清掃会社に委託する場合
- 運送会社が配送業務の一部を別の運送会社に委託する場合
下請法における元請業者の禁止事項
下請法では、元請業者の義務や禁止事項について細かに定められています。下請業者の了解を得ている場合や違反の意識が無い場合でも、下請法に違反には、十分注意が必要です。
下請法での元請け業者の禁止事項は以下です。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
引用元:政府広報オンライン|了承を得ていてもNG!「親事業者の禁止事項」
※下請法の条文では、元請業者/発注元が「親事業者」、下請業者/発注先が「下請事業者」と記載されます。
下請法における元請業者の義務とNG行為
下請法では、下請取引の公正化や下請事業者の利益保護のために、元請業者に4つの「義務」が課されています。
- 書面の交付義務
- 書類の作成・保存義務
- 支払期日を定める義務
- 遅延利息の支払義務
引用元:公正取引委員会|親事業者の義務
※下請法の条文では、元請業者/発注元が「親事業者」、下請業者/発注先が「下請事業者」と記載されます。
下請法の違反を確認するためには、上記の禁止事項や義務が果たされているかを確認する必要があります。以下では、各条文と共に義務とNG行為を解説します。
【1】下請代金の支払期日を定める義務
下請法2条の2「下請代金の支払期日」では、下請事業者の資金繰りの保護や公正な取引の促進のために、元請業者が下請業者に対して、下請代金をいつまでに支払うかを明確にする義務が定められています。
親下請代金の支払期日は,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず,親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して,60日の期間内において,かつ,できる限り短い期間内において,定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が,前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
下請代金の支払期日の義務に関するNG行為
元請業者には、下請業者からの物品の受領・納品などを受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定める必要があり、支払い期日内に報酬を支払わないことや、支払いの遅延、支払いを不当に遅らせることは、NG行為に該当します。
【2】書面を交付する義務(3条書面)
下請法の第3条では、元請業者は、下請業者に対し、製造委託等(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)をした場合は、すぐに取引内容が明確に記載された書面(いわゆる3条書面)を下請業者に交付する義務が定められています。
また第3条では、下請事業者の承諾を得ている場合には、書面(紙)以外で、電子的な方法による情報提供も認められるとされています。
親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,直ちに,公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容,下請代金の額,支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は,前項の規定による書面の交付に代えて,政令で定めるところにより,当該下請事業者の承諾を得て,当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において,当該親事業者は,当該書面を交付したものとみなす。
書面を交付する義務に関するNG行為
交付された書類に、発注内容や下請代金の金額、支払期日、支払方法など必要事項が記載されていない場合や、書面自体が交付されていない場合はNG行為に該当します。
【3】取引に関する書類を作成・保存する義務
交付された書類に、発注内容や下請代金の金額、支払期日、支払方法など必要事項が記載されていない場合や、書面自体が交付されていない場合はNG行為に該当します。
親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,公正取引委員会規則で定めるところにより,下請事業者の給付,給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては,下請事業者がした役務を提供する行為の実施),下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し,これを保存しなければならない。
書類の作成・保存の義務に関するNG行為
書類を作成していない場合や書類に必要事項が記載されていない場合、また、書類は作成したもの2年未満で破棄した・2年間保存しなかった等の場合はNG行為に該当します。
【4】遅延利息の支払い義務
下請法第4条の2では、元請業者が、事前に定めた支払い期日までに下請代金の支払いを行わなかった場合、支払い遅延日数に応じて、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が定められています。
親事業者は,下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは,下請事業者に対し,下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
遅延利息の支払い義務に関するNG行為
給付受領日から60日以内の事前に定めた日程で下請業者に支払いを行わなかった場合は、NG行為に該当します。「給付受領日から60日を経過した日」を起算点とする、支払いが遅延した日数に応じて遅延利息(年率14.6%)を払わなければなりません。
下請法に違反した場合のペナルティとは?
下請法違反の疑いがある事業者は、公正取引委員会の調査の対象となります。調査によって違反が発覚した場合は、禁止行為の取りやめや原状回復、再発防止措置を求める正式な法的措置として一定の拘束力を持つ勧告を受けることになります。
この勧告に従わない事業者には、民事上でも賠償請求となり、50万円以下の罰金が課せられるなど、重いペナルティが科されます。違反の程度が軽い場合は、勧告に至らないパターンもありますが、指導が入り改善報告書の提出が求められます。
また、下請法の要件を満たさなくとも、独占禁止法の要件を満たす場合、「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が出される可能性があります。
下請法違反があった場合はどうするべきか
下請法違反については、自社だけの判断では元請業者にペナルティを科すことはできないため、下請法に沿って現状を整理し、書類などの証拠を揃えたうえで、専門機関へ相談しましょう。また、元請業者側が下請け業者に依頼する場合は、下請法を遵守するよう十分に注意しましょう。
公正取引委員会の公式ホームページや、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「政府広報オンライン」では、下請法のわかりやすい解説や、下請法違反の確認のポイント、全国各地の相談先が掲載されたページも用意されているので、まずはこれらのサイトを確認することをおすすめします。
下請法違反を感じたら「政府広報オンライン」をチェック
下請法を詳しく知るなら「公正取引委員会 HP」をチェック
引用元:下請法とは|公正取引委員会
まとめ
フリーランスや個人事業主が企業から仕事を請け負う際、力関係的に元請側(企業側)が強いパターンが多く、下請法に違反されている疑いがある場合や、明らかに違反されているものの、指摘・告発することが難しい場合もあります。しかし、泣き寝入りしてしまうと適切な報酬を得られなかったり、同事業者との今後の取引に影響する可能性もあるので、自社を守るためにも、下請法のポイントや相談先を知っておくことが重要です。
また、フリーランスや個人事業主への仕事を委託する際に適用される「フリーランス新法」が2024年11月に施行されており、下請法との異同を確認しておくといいでしょう。
格安&簡単な電子契約『クラウドコントラクト』を試してみませんか?
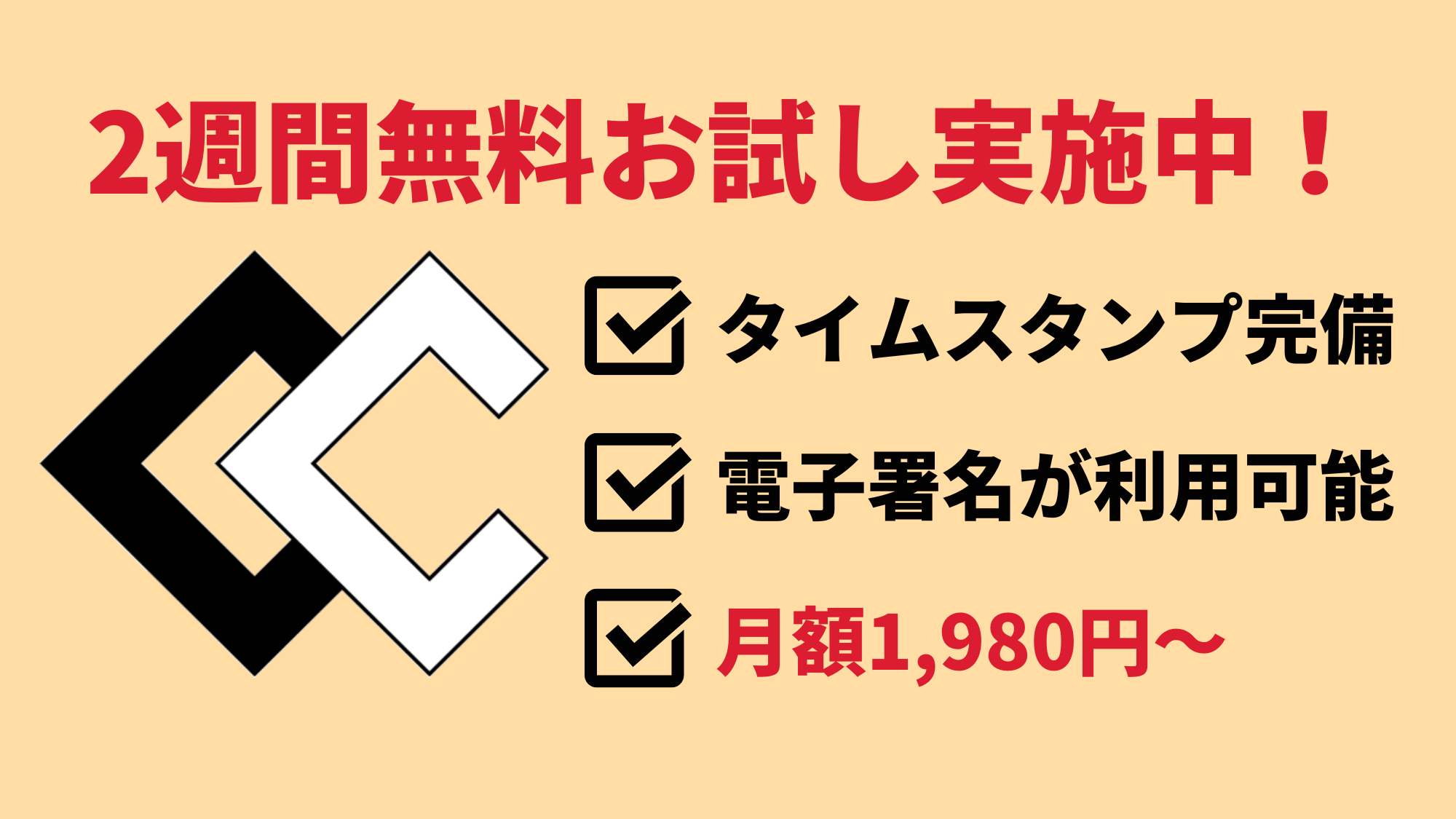
中小企業様や個人事業主様に最適な、格安で必要な機能がそろったシンプルな電子契約サービス『クラウドコントラクト』では、2週間無料トライアル(お試し利用)を実施しています。
タイムスタンプや電子署名といった必須機能はもちろん、相手への確認の手間を削減できる契約状況の確認機能などの便利な機能を備えつつも、直感的に使用できるシンプルなサービス。よって、印紙税や郵送代などのコストや作業時間を手軽に削減することが可能です。
また、カスタマーサポートも充実しており、電話やチャットでのお問い合わせも対応しておりますので、操作に不安がある方も安心してご利用いただけます。
電子契約をもっと知る
弁護士監修の使える契約のノウハウを発信中!